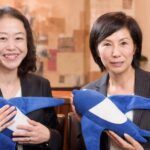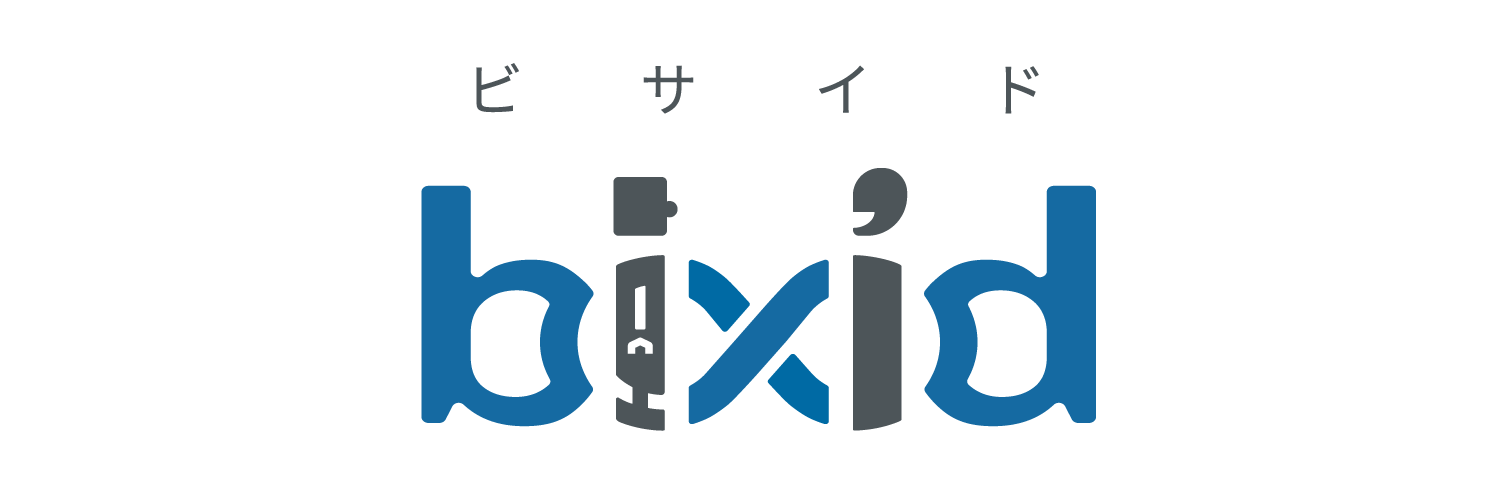前回のコラムでは、納税者と課税当局の間では、いたちごっこにも似た現象が起こっているということを書かせていただきました。
今回のコラムはまさに今後も続くと予想される「国外財産に対する課税強化」について、今回と次回の2回に分けて、ある2つの事件を振り返りながらご紹介させていただきます。
今回取り上げるのは武富士事件です。
武富士事件とは?
贈与税回避スキームというと、平成12年度税制改正で封じ込まれた「非居住者に対する贈与スキーム」で最高裁判所まで争われた「武富士事件」(平成23年2月18日最高裁判決)が有名です。この事件について振り返ってみましょう。
この事件は、武富士前会長夫妻(国内に居住)が香港に居住していた長男に国外財産を贈与したことに対して贈与税が課税されるか否か争われた事件です。この贈与に対して東京国税局は申告漏れを指摘しました。追徴税額は 約1,300億円にものぼりました。
この事件の争点は、たった一つ“長男が居住者か非居住者か”(日本に住んでいるのか海外に住んでいるのか)という点でした。つまり、生活の本拠が日本にあるのか香港にあるのかということが争われたのです。
当時の税法を振り返る
この事件をご理解いただくためには当時の税法を少し検証する必要がありますので、少し書かせていただきます。
国外の財産が関連する贈与税(相続税も同様)の納税義務の範囲については、武富士事件で1段階、そして、次回で取り上げる中央出版事件で1段階厳しくなっています。つまり平成12年以降で2回の大きな改正が入っています。ここをまずイメージしていただいて再度納税義務についてご説明させていただきます。
まずは、平成12年3月末までの納税義務者の話です。
「武富士事件」により改正が行われる前の規定では、もらう側の人が非居住者(※詳細は後述)である場合には一律に国内財産のみが課税の対象とされて、国外財産は課税の対象外とされていました。
そのため、一時的に財産を国外に移転して、国外に子供を居住させこの国外財産を贈与するスキームが一般的に利用されるようになったというわけです。
これを封じ込めるために、改正を行い日本に居住していなくても、財産をもらう人が日本国籍を有していて「もらう人、または、あげる人が5年以内に日本に住所を有している」を満たす場合には、居住者と同様にすべての財産が課税財産となるという“非居住無制限納税義務者”という区分を設けました。
武富士事件で問題となった贈与は、この改正が平成12年4月1日から改正となることから、その直前の平成11年12月に駆け込みで行動したと思われます。
居住者・非居住者とは?
先ほどの話に戻りますが、この裁判の争点は長男が居住者か非居住者かというところのみでした。
居住者か非居住者かというのは所得税法で下記のように規定されています。
居住者:国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。(所得税法第2条第1項第3号)
非居住者:居住者以外の個人をいう。(所得税法第2条第1項第5号)
長男の居住実態とは?香港と東京の二重生活!?

では、肝心の長男はどのような状況だったのでしょうか?
裁判によると、
- 年間日数のうち約65.8%は香港に滞在していたが、日本滞在中は出国前の都内の自宅(部屋は出国前の状態のまま維持されていた)で生活していた。
- 香港での居住はサービスアパートメント(ホテルとアパートの中間的な機能のもの)であった。
- 生活費等の支払は日本、香港双方の口座から行われていた。
というような実態であったようです。
この長男の生活実態について、課税庁は長男の香港居住の客観性を否定して、実際の住所は日本にあった(つまり居住者である)と認定し贈与税を課税することにしました。これに対し、長男は処分の取り消しを求めて裁判を起こしたというわけです。
地裁では長男(納税者)勝訴、しかし、高裁では・・・
この結果、東京地裁では納税者(長男)が勝訴しました。
しかし、東京高裁では一転、納税者が敗訴しました。
東京高裁では「贈与時に生活の本拠は国内にあったとして行った課税処分は適法」と述べ、東京地裁の判決を取り消しました。
この高裁の裁判では、
- 家財道具は日本の自宅に置いたままであった
- 日本が職業活動上最も重要な拠点であった
- 元会長の後継者として日本での生活が予定されており香港を生活の本拠とする意志は強くなかった
などの理由から日本の居住者とされたわけです。
最高裁で逆転判決。約2,000億円が返還
その後、長男は、高裁判決を不服として上告しました。
最高裁判決において裁判長は過去の判例を踏まえ「客観的に生活の本拠としての実態を備えているか否かによって決めるべきである」と指摘しています。
また、贈与前後の期間の3分の2を香港で過ごし業務に従事していたことなどを挙げ「贈与税回避の目的があったとしても客観的な生活の実態が消滅するわけではない」として平成23年2月18日、課税を適法とした高裁の判決を破棄し、納税者側の逆転勝訴が確定しました。
そして、この逆転勝訴により長男にはこれまでの納税分のほかに、利子にあたる還付加算金約400億円などを含めて計約2000億円が返還されることになりました。これは個人への還付額では過去最高額だそうです。
租税法律主義に基づく判決
この武富士事件の最高裁判決の価値は裁判長による次のような補足意見にあるといわれています。
「一般的な法感情の観点から結論を見る限りでは違和感を生じないわけではない。しかしそうであるからといって、個別否認規定がないにもかかわらず、この租税回避スキームを否認することには、やはり大きな困難を覚えざるを得ない。納税は国民に義務を課するものであるところからして、この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず、これを規定する条文は厳格な解釈が要求されるのである。
明確な根拠が認めらえないのに、安易に拡張解釈、類推解釈、権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。そして、厳格な法条の解釈が求められる以上、解釈論にはおのずから限界があり、法解釈によっては不当な結論が不可避であるならば、立法によって解決を図るのが筋であって、裁判所としては立法の域にまで踏み込むことはできない。後年の新たな立法を遡及して適用して不利な義務を課すことも許されない。
結局、租税法律主義という憲法上の要請の下、法廷意見の結論は、一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれどもやむを得ないところである。」
このように、この裁判長の補足意見には日本国憲法第84条と第30条で定められている「租税法律主義」という基本的な原理に基づいて行われた裁判であることが忠実に表れています。
租税回避スキームであることは認知されつつも、税を課すのであれば法律で行うことが必要であるというルールの重要性がとてもよく伺える裁判だと思います。
現行の贈与税(相続税も同様)の納税義務者については、先ほど少し触れましたが中央出版事件をきっかけに再度改正されました。平成25年4月1日以後の贈与に関しては、贈与者(財産をあげる人)が国内に住所を有している場合には、国内財産・国外財産問わず課税されることとなりました。
これは、次回取り上げる中央出版事件により改正されたものです。
次回はこの中央出版事件についてご紹介させていただきます。
参考資料:
- 『資産フライト「増税日本」から脱出する方法』,文藝春秋,山田順
- 『武富士最高裁判例の総合的研究~租税回避と住所認定の是非~』,MJS租税判例研究会,中央大学商学部教授大淵博義
- 『武富士事件の最高裁判決』,2011年2月PwC資産税ニュース