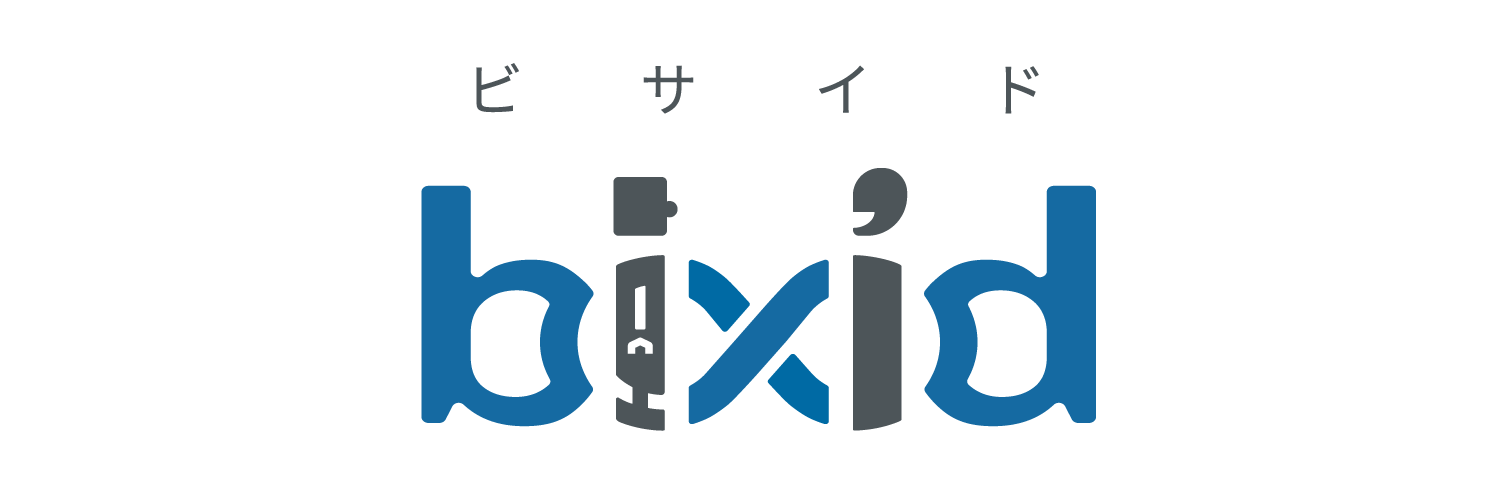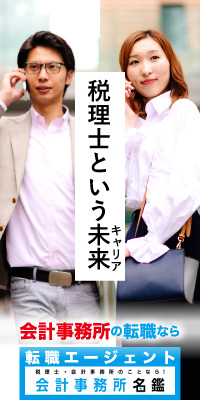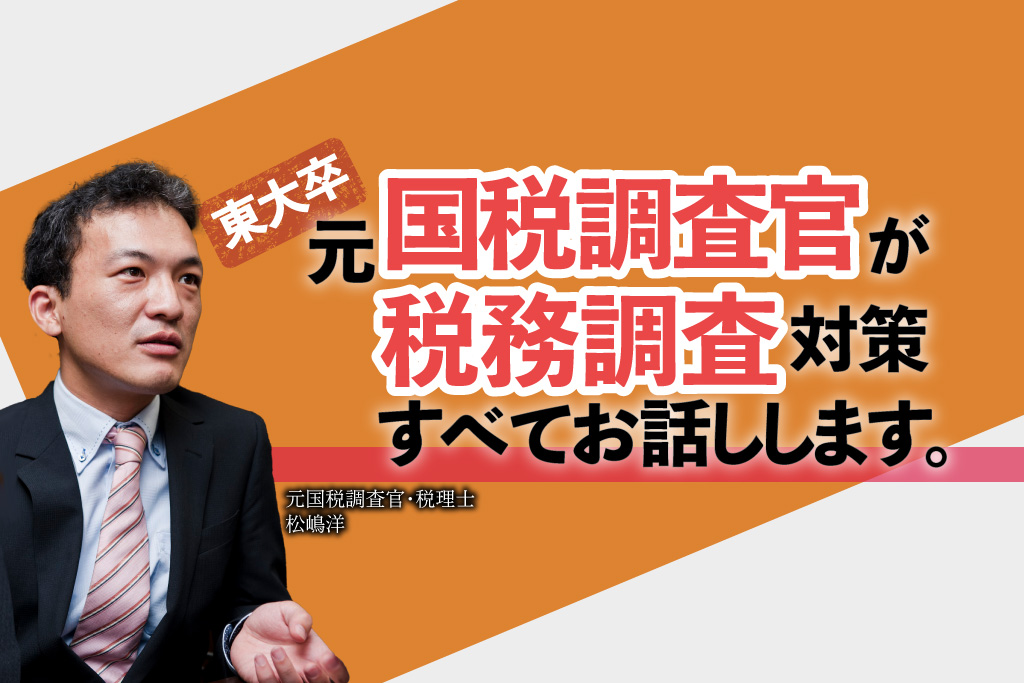
税法には実質基準という考え方があります。
税金は名実ともに儲かった者に課税すべきです。このため、税金に関する事実認定については、法律の形式にとらわれることなく、実質的に判断をしなければならないという原則を意味します。
具体例として、相続税の名義預金が分かりやすいです。
子供名義の預金は法律の形式では子供の財産となります。
しかし、その預金の原資であるお金を被相続人である親が出していたり、預金の管理をその親がやっていたりしたのであれば、実質的には親の預金ですので親の相続財産になることがあります。
この考え方は税の常識ですのでよく知られていますが、実質基準といいつつ形式を重視する場合もあります。
典型例が、輸出や輸入の消費税の取扱いです。輸出商品の売上は消費税が免除され、輸入時に課税される消費税は消費税の控除ができますが、これらの特典を受けられる者は、原則として輸出申告や輸入申告をした者に限定されます。
商品の輸入を例にとりますが、輸入代金やその消費税は自社で全額負担するものの、外部の業者にその手続きを丸投げし、輸入申告についてもその業者の名義で行うとします。
この場合、商品を実質的に輸入したのは代金を負担する自社であり、外部業者ではありませんが、輸入消費税について、その控除ができるのは輸入申告の名義人である外部業者になります。
輸出にしても輸入にしても、海外が絡むと消費税の取扱いが優遇されますから、対象者の要件を厳しくする必要がありますので、このような取扱いになっているのです。
同様に、法人税の役員給与についても形式が重視されることがあります。
役員給与は、税法上の限度額を超えると法人税法上経費にはならないとされますが、その限度額は役員の会社法上の肩書きに応じて決まります。
この点、「監査役」でありながら、実質的に「取締役」の仕事をしていた役員に対する限度額が問題になった裁決があります。
この事例において、納税者は実質的に取締役なのだから限度額は取締役の金額とするべき、と主張しました。
しかし、審判所は肩書きが監査役である以上は、会社法上その肩書きに則った権限しかないはずで、そうなると取締役としての実質に関係なく、監査役としての金額が限度額となると判断しました。
監査役の報酬は取締役よりも低額であることが通例ですので、この事例において大きな不利益を会社は被ることになりました。
実質基準は税法の常識ですから、このようなミスは実務ではよく生じます。
ある時は実質、ある時は形式で物事を判断しないといけないのが税の難しいところで、この点税務調査でもよく問題になります。
どちらを重視するべき事案か、その判断基準は明確ではなく、過去の事例や法律の考え方に沿ってケースバイケースで見る必要がありますので、常日頃から判例等に目を通しておく必要があります。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs
⇒「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら
税務調査対策ノウハウを無料で公開中!
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
 元国税調査官・税法研究者・税理士
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。